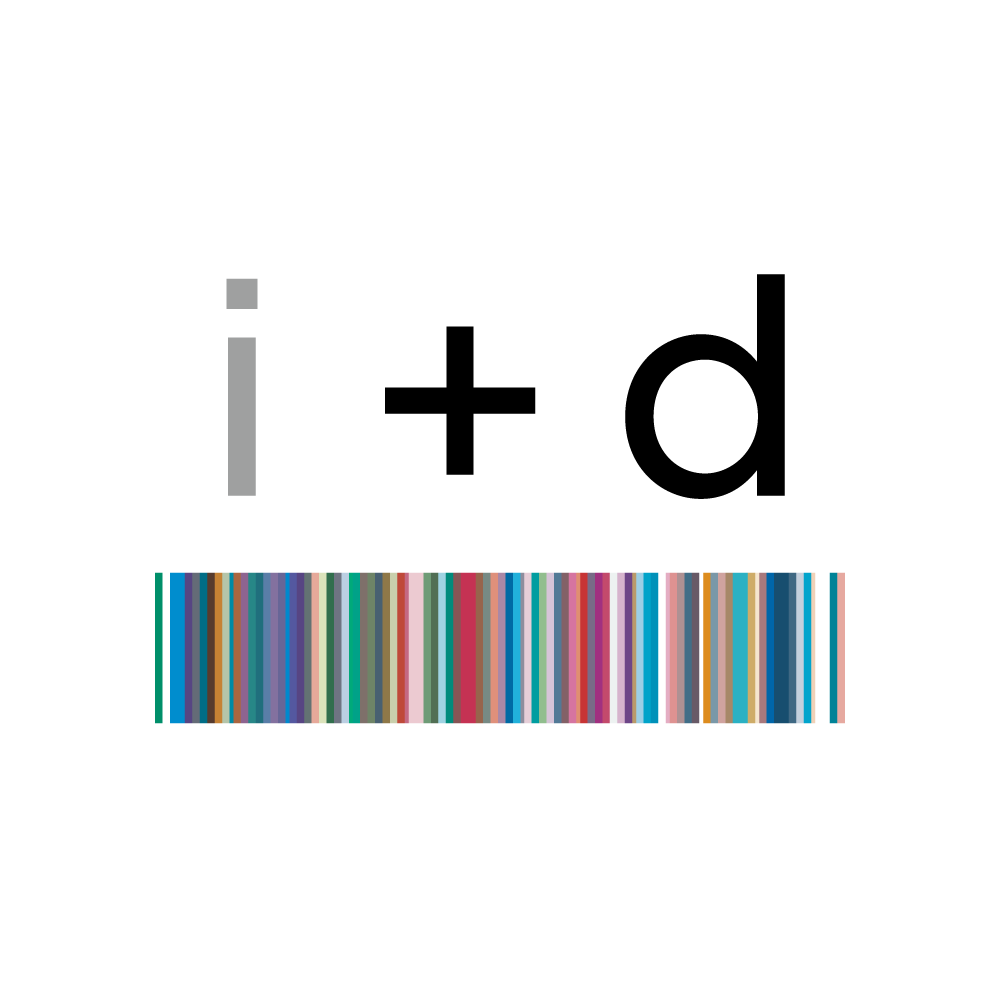対談10 河邉優子さんに聞く、就学支援のすすめ
「みんなで就学活動」は、支援の必要なお子さんが小学校に就学する時にご家族が遭遇する困難や悩みを知るとともに、自分たちにとってより良い選択を描きながら就学できるようにするための“こうしよう”術を、みんなで対話し、つくりあげていくプロジェクトです。
ここでは高橋真さんが各分野の専門家を訪ねて聞いた、多様な視点と具体的なアドバイスをご紹介していきます。
第10回目にご登場いただくのは、第二東京弁護士会の河邉優子(こうべ ゆうこ)さんです。第一子が医療的ケア児であることを理由に保育園を断られた体験をきっかけに、就園就学問題に取り組んでいる弁護士です。相談や講演の他、東京弁護士会と第二東京弁護士会の合同にて、医療的ケア児を含む障害のあるお子さんの就園就学に関する電話相談「就園就学ホットライン」を開催するなど、法律の専門家という立場を通して課題解決に取り組む河邉さんに、現時点で問題視していることなどを教えていただきました。
河邉 優子(こうべ ゆうこ)
2010年3月 東京大学法科大学院修了、2012年12月 弁護士登録、第二東京弁護士会所属。医療的ケアを要する子を出産し、保育園から受入れを拒否された経験をきっかけに、障害のある子どもの権利擁護に取り組むようになる。日本弁護士連合会人権擁護委員会特別委嘱委員、同会貧困問題対策本部委員。主な著書として、『子どもの福祉・医療・権利擁護相談支援ハンドブック』(共著、新日本法規出版、2023年)、『障害者をめぐる法律相談ハンドブック』(共著、新日本法規出版、2020年)、『子どもの権利ガイドブック【第2版】』(共著、明石書店、2017年)などがある。
目次
80年前の裁判に教わった「ショックの理由」
高橋 真(たかはし・ちか。以下、高橋さん) ご出産後は、弁護士としてお仕事でも就学活動の問題に取り組んでいらっしゃるんですね。
河邉さん 弁護士になった当初は貧困問題などに取り組もうと思っていたのですが、出産した子どもが重度の障害のある医療的ケア児でした。9年前のことなので、今ではさすがに減っているとは思いますが、病院の先生に「医療的ケア児の場合、保育園はきっと入るのが難しいでしょうし、お父さんかお母さんが常に付き合う生活になるのでお仕事を調整するなどしてください」と言われたことを覚えています。
それを告げられた時もショックでしたが、もっと辛かったのは保育園を断られた時でした。自分の子がまるで、この社会で生きることを歓迎されていないように感じましたし、他の子と同じような場で育てようとすること自体があまりにも簡単に否定されてしまうことを肌身に感じてしまったんです。それで、こんなショックを受ける人を少しでも減らすことができたら、と思って職場復帰後も就園就学について取り組むようになり、ときどき相談窓口を開く、ということをしております。
高橋さん 同じ痛みを体験した弁護士さんに相談できるのは、保護者の方も心強いですね。
河邉さん 保育園を断られた時、自分がショックを受けている理由がどこにあるのか、考えました。例えば役所の方に「こんなに重い障害のある子のお母さんは大抵仕事を辞めていますよ」とか「地域の保育園に入れるのは、お子さんがかわいそう」と言われたり、またインターネットなどにもインクルーシブを願うことを「親のエゴ」と批難する意見が散見されますよね。そんな中で、本当のところ自分は一体、何に対してショックを受けたのだろうか、と考えたんです。
その頃、障害者の問題に取り組む別の弁護士からある判例を教えてもらいました。それは1950年代のアメリカで行われた「ブラウン判決」と呼ばれる、人種差別に関する裁判です。奴隷制度が撤廃された当時、「分離すれども平等」という考え方をしていたアメリカでは、学校に行く権利が全員に認められてる一方で、黒人と白人は同じ学校に入ることが許されず、リンダ・ブラウンという小学校3年生の女の子はわざわざ家からとても遠い学校に行かねばなりませんでした。家から近い白人たちの通う学校に入れないのは差別だと訴え、アメリカの連邦最高裁で満場一致で勝訴したんです。その判例では「分離するということが、分けられた者の心に劣等感を与え、取り返しのつかない形で心に影響を与える可能性がある」と書かれています。
それを聞いたとき、保育園を断られた時の自分の気持ちはこれだ、と思いました。あなたは入れませんよと言われることそのものが、この子の尊厳を傷つけて、どれほどの影響を与えるか。それは本能的にショックなことであり、あるべき状態ではない事態だ、と腑に落ちたんですね。
ただこれは決して、支援学校に通うことを否定しているわけではないんです。個々の当事者がどちらも十分に選べる状況の中で、地域の小学校ではない学校を選ぶ、その判断はもちろん間違ってなんていません。問題は、行政機関が強制的に「あなたは地域の学校に入れません」と個人を否定することにあります。現状ではそのデメリットが全く考えられていないんです。当事者が地域の学校に通いたいと言っているにもかかわらず、行政機関がそこから排除することは、子どもの心に取り返しのつかない傷を負わせてしまう可能性がある、そんな暴力性があることを、行政機関はもっと認識すべきだと考えています。
世界が求める、インクルーシブ教育の定義
高橋さん 日本におけるインクルーシブ教育がなかなか進まない背景には、障害の有無によって学校を分けることで考えられる弊害が認識されていないんですね。
河邉さん そうですね。欧米ではかなり以前からインクルーシブ教育が実践されていて、以前の記事で崔さんもお話されていましたが、日本を含めた世界184ヶ国が批准する「障害者権利条約」では一貫してインクルーシブ教育の大切さがうたわれています。
残念ながら現状が伴わない事例が続く日本に対して、国連の障害者権利委員会は2022年9月に総括所見を出しました。これは日本の障害者の権利に対するいわば”ダメ出し”で、特にインクルーシブ教育に関しては「地域の学校が障害のあることを理由に入学を拒否することを禁止する、『拒否禁止』の法律を作りなさい」と、強い勧告がされたんです。現在の世界基準として、いかに国連がインクルーシブ教育の実現を求めているかが分かる事例だと思います。
高橋さん 先ほど、教育の場を分けること自体が問題であるというお話とともに支援学校の選択にもふれられていましたが、インクルーシブ教育の推進と、支援学校への入学について、どのようにバランスを取って考えたら良いでしょうか?
河邉さん 現状の日本では、国連が求めているインクルーシブ教育を想像しづらいのは事実だと思います。そもそも障害者権利委員会が定義しているインクルーシブ教育は、障害のある子を単に地域の学校に通わせることではありません。障害のある子が地域の小学校に入り、他の子どもたちと交流しながら、差別のない環境で同じように教育を受けること。そして、その子に必要な支援は教室内で受けられること。それがインクルーシブ教育だと定義しています。
しかし学校を分けることが前提とされてきた日本で、国連の定義だけを盾にして強く学校側に主張することはとても難しいです。それほどまでに「分ける」ことが前提になってしまっているので、まずは学校を分けることの不利益性を考える必要性があるでしょう。
毎日を一緒に過ごす。有益な時間は双方向
高橋さん 現状だと、障害のあるお子さんを育てている保護者の多くは、地域の学校に行ってもなかなか思うような対応をしてもらえず、そこで受けるダメージの大きさを理解しています。その結果、今までの慣習に沿って分けられた教育を選んだり、共に学ぶイメージそのものを体験していないため、国連のいうインクルーシブ教育が想像しづらいのかもしれません。
河邉さん おっしゃる通りです。本当にインクルーシブ教育を実現させるには、日本社会の価値観を変えて、学校の在り方を変える必要がある。もっと大きなことを言えば「何のための教育か」というところから考え直す必要があると思っています。
なぜなら日本の学校ではどうしても、ある一定の基準に沿ってみんなと同じことを同じようにできることが是とされているからです。もちろん読み書きや計算もとても重要な要素ですが、子どもたちに育んでほしい能力って本当にそういうことでしょうか?まずは、地域に生きる人々の多様性を認め合って、いろんな人が生きている中で他者も自分も認めること。わたし自身、子どもにはそういう価値観を学んでほしいと思っています。
高橋さん 学校の役割そのものを問う、ということですね。わたしの娘は地域の小学校に通ってるんですが、スキップや縄跳びが苦手で、体育の授業や遊びなどうまく一緒にできないことがあります。でも障害のないお子さんでも同じように縄跳びができない子はいるので、障害があるからではなく、障害がない子でも不得意な子はいて、その子も楽しめるような工夫はあったほうが良い。誰でもその授業での学びをその子どもなりに実現できることが重要であることは同じなんですよね。
河邉さん そうですね。うちも保育園の頃、毎年恒例で行われていた大縄跳びが廃止になったことがありました。先生方は違う理由を話していらっしゃいましたが、うちの子に気を遣ってくれたように感じました。それで他の保護者の方々に「楽しみにしていた恒例行事なのにすいません」とお伝えしたところ、子どもが理由でできなくなったことではないし、むしろ普段の生活の中で○○くん(うちの子)がいることで学んだことが多い、と皆さんおっしゃってくださいました。中には丁寧に、うちの子に対するお礼の言葉やお手紙までくださった保護者の方も数名いらっしゃいました。お世辞もあったかもしれませんが、園の先生方からも、大縄跳びが無くなって悲しんだ子どもたちの声はなかった、とお聞きしました。
それにわたし自身も、小学校の頃、同じクラスに障害のある子がいたんです。ある時、その子がからかいの対象になってしまったことがありました。担任の先生は本当に心を痛めて、みんなの前で泣きながらその出来事をみんなに問いかけ、いけないことだ、ということを強く伝えて叱ってくれました。今でも本当によく覚えている出来事です。わたしはその時、何もできず、そのことを非常に申し訳ないと思っており、その申し訳なさも、今、私がこうした活動をしている一つの理由になっています。あの子がクラスにいてくれたからこそ気づけたことや、理解できるようになったことはたくさんあると感じています。今、障害のある子の子育てをイメージをもちながらできているのも、あの子がいてくれたおかげだとも感じています。幼少期にどんな仲間と一緒にどんな実体験を積むか、ということは、全ての子どもにとって重要な人生経験であり、障害のある子どもと一緒に学び育つことは、障害のない子どもから奪ってはならない権利だとも思うんですよね。
高橋さん よくわかります。私も小学校の6年間は医療的ケアが必要な、電動車椅子に乗った同級生がいました。言葉も話せないんだけど、でも学校でいつも一緒にいると、機嫌の良い時とわるい時がわかったりするようになるんですよ。そして好きなものがあったり、家族とのふれあいを見る中で、どんな人でもその人らしく生きていていい、ということが子どもながらに何となく理解していたと思います。私も、自分の子のダウン症に対して受容が早かったのは、当時あの子がクラスにいてくれたおかげだと思っています。
河邉さん 接点があると受容が早いですよね。きっと現状ではご本人や保護者はたくさんの苦労をされてきていると思いますが、地域の学校に通ってくれているご本人には同じ学校に通わせてくれて本当に有り難うと言いたいし、保護者の方には、その決断をしてくれたこと、さらにいえばその子を産んでくれたこと、一生懸命育ててくれていることにも有り難うございますと言いたいです。
「できること」は際限なくあるから
高橋さん 教育の意味を問うという河邉さんにとって、理想の教育とはどのような教育ですか。
河邉さん 思い描いている理想は、お互いを認め合うことを最優先にした教育です。クラスの中にはいろんな背景の子どもがいて、それぞれ必要な支援がクラスの中で満たされて、障害のない子たちにとってもそれが当然のことだと認識されていること。もちろん、障害のある子どものための場のニーズもありますが、それはあくまでも、みんなが待っているホームグラウンドのクラスがある上で、プラスアルファとして存在すべきだと考えています。
日本の現状が国連から勧告を受けたと言いましたが、自治体によってかなり違いもあるんです。日本にも長い間インクルーシブ教育を実践してる地域はいくつもあって、私も視察などでお邪魔することがあります。
高橋さん 大阪の豊中市や箕面市では、インクルーシブ教育が地域の方々にも浸透しているそうですね。
河邉さん 進んだ自治体では、バギーに乗って人工呼吸器をつけた重度の医療的ケア児が地域の小学校に入学希望をした時も、「はい、わかりました」と、とんとん拍子で進学が決まる、と聞きました。
学校の先生に聞いたお話では、クラスで毎日一緒に過ごしているうちに、子どもたちもその子を自然に受け入れるので、一緒に過ごすためにはどうしたらいいか、と子どもたちの方から進んで考えるようになるそうです。
ひとつ、すごく印象的だったお話は、あるクラスの演劇発表の話です。童話の「おおきなかぶ」のお芝居をすることになり、バギーに乗って自ら動きが取れない医療的ケア児にどんな配役がいいか?と子どもたちが話し合った結果、なかなか抜けないおおきなカブ役、つまり主役になったそうなんですよ。

高橋さん それを子どもたちがみんなで考えたというところも素晴らしいですね。
河邉さん 障害のある子の「できないこと」を挙げたらたくさんあるかもしれないんですけど、逆に「何ができるだろうか」と考えると、それもまた際限なくいろいろあるんだとわかりますよね。
インクルーシブ教育が先進的な自治体では、担当者が「この子は無理だ、と考えることはしないし、無理だと思われることをできるようにするのが学校の役割だと思っています」とおっしゃっていました。本当にその通りだと思います。まだやったことないのに学校側が「インクルーシブ教育は無理だ」と言ってしまったら、学校の存在意義と矛盾してると思うんです。実践している自治体さんは「できます」とおっしゃいますし、教育現場にはぜひとも、まずは実践してみることを望んでいます。
高橋さん 少しずつでも、先進的な自治体からいい影響を受けて、変化する自治体が増えていってほしいですね。
河邉さん 普段、学校側と交渉する際に先進的な自治体の話をしても、拒否感を示す方も少なくありませんが、でも実践できている自治体があるという事実は強力です。実際に、本当に少しずつですが変化を感じることもたくさんありますし、一気に全てが変化することは難しいので、少しずつでも広げていこうと考えて取り組んでいます。
高橋さん 教育の方向性や考え方を柔軟に変化させながら、みんなが自分で「通いたい」と思う学校に入れるようにしていきたいですね。今日はどうもありがとうございました。